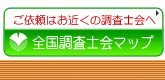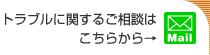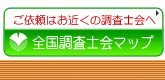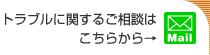|
 |
| ご相談項目のご案内 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| トラブル調査が必要なとき
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| サイトの運営について
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
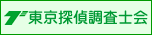
探偵・興信所へのトラブル調査依頼
|
| |
|
|
|
|
契約とは、「契約書」を交わした約束事だけとは限らず、普段のちょっとした買い物でも契約は存在しています。スーパーでひき肉を買う。宝飾店で高価な指輪を買う。コンビニでおにぎりを買う。100円ショップで洗面器を買う・・・。こういった買い物(売買取引)では、いちいち契約書に印鑑を押捺したりサインすることなどまずあり得ませんが、「これください」「はい○○○円です。ありがとうございます」といった会話が、すでにお互いの「意思表示が合致した」ということが根拠となって契約が成立したことになります。
金融機関からの借金や住宅をはじめとする不動産売買など、多額の取引きに契約書が交わされるのは、後に支払いがされない、商品が届かないといった不履行が生じた時に被害が大きいことから、法律で義務づけられているだけで、金額の大小を問わず、売買には契約を通じて取引されています。
 自分の意志で決定し合意した上で契約は成立したわけですから、買う側も売る側もその契約を守らなければなりません。その意味では反対に、自由な意思で判断できなかった契約には拘束力はなく、そもそもそういった場合の契約は契約とは言えず、意思無能力者(幼児や痴呆を患っている人)の締結した契約(書)は無効となります。 自分の意志で決定し合意した上で契約は成立したわけですから、買う側も売る側もその契約を守らなければなりません。その意味では反対に、自由な意思で判断できなかった契約には拘束力はなく、そもそもそういった場合の契約は契約とは言えず、意思無能力者(幼児や痴呆を患っている人)の締結した契約(書)は無効となります。
契約が成立すると、たとえば売買契約した当事者にはそれぞれ義務と権利が生じ、買う側は代金を支払う義務と商品を受け取るなどの権利。売る側は商品を引き渡す義務と代金を回収する権利を得ます。それら契約の内容(金額や支払い方法、商品の受渡し方法、期日など)は、基本的に契約者同士の意志に基づいているものが前提のはずですが、どちらか一方(多くは売る側)があらかじめ契約内容を決めて書面にし約款として提示していることが多く、もう一方(多くが買う側)がそれに対して承認の証に捺印やサインをするといった形が一般的であり、そこにこそ契約トラブルへの落とし穴があるのです。
面倒だからと言って内容をよく読まずに理解しないまま捺印したりサインしたりすれば、その時点で契約内容を理解し、合意したことになりますので、後に理不尽な結果を招いたとしても、それが契約上の約束にそったものならば「あなたの意思による責任」と見なされ、何の言い訳もできません。契約の捺印やサインには十分な慎重さと注意深さが必要です。
|
|
|
|
|
|
契約が締結されたからといって、それが全てではないことも知っておく必要があります。特に消費者契約では「クーリング・オフ制度」があり、特定のもので一定の期間内であれば無条件に契約を解除することができます(【トラブルお役立ち情報】クーリングオフ参照)。マルチ商法や内職商法、或いは人身売買、差別的な労働契約など公序良俗に反するような合意は契約の拘束力を認められません。
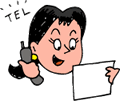 また、相手方が契約を約束通り実行しない(債務不履行)場合は、裁判所などによって強制執行するか、契約そのものを解除することができ、いずれにおいても損害賠償を請求することが可能となります。 また、相手方が契約を約束通り実行しない(債務不履行)場合は、裁判所などによって強制執行するか、契約そのものを解除することができ、いずれにおいても損害賠償を請求することが可能となります。
契約は「あなたの意思による責任」ということを申し上げましたが、まだ救う道は開かれていますので、もう一度契約内容を精査し、そこではまだあきらめないことが肝心です。
|
|
|
|
|
|
未成年者の契約には「法定代理人」の同意が必要です。法定代理人というと難しく聞こえますが、通常は親権者、つまり親の同意を必要とし、逆に同意がなければ契約は成立しません。
一方、未成年者が成人であるとウソをついたり、両親の同意がないに関わらず同意があったとウソをついたりなどして、取引の相手を騙して締結した契約の場合は、未成年者側に契約を取り消す権利はほぼありません。
未成年が契約トラブルに陥った場合、この前提を踏まえて契約書をよく見直し、トラブルの解決にあたっては当事者間で処理しようとせず、専門家にまず相談することをお勧めします。
|
|
|
|
|
|